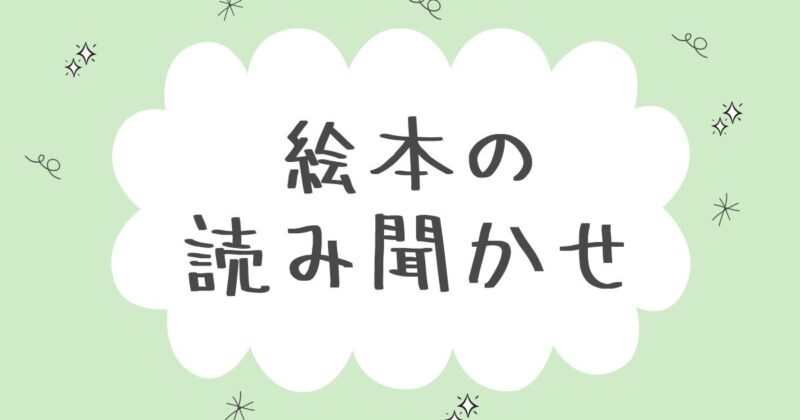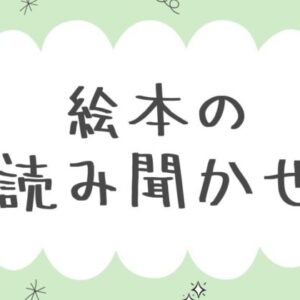絵本「かにむかし」のご紹介です。
この絵本を図書館で読み聞かせをしてきました。
この記事でわかること↓
キャラクターグッズも販売中
無料ためしよみ
かにむかし「作者」と「出版社」
文:木下順二
絵:清水崑
出版社:岩波書店
かにむかし「あらすじ」
柿のたねをひろったカニは、その種を庭にうめて、大きな柿の木に育てます。
「はよう うれろ かきのみ、うれんと、はさみで、もぎりきるぞ」
柿は、たくさんの実をつけました。
カニは、うれしくてたまらない。
でも柿の実をとりたくても、はいのぼっては落ち、はいのぼっては落ち。
それをみていたサルが、ひょいひょいっとやってきた。
サルは、助けてくれるどころか、次々にうまそうな柿を食べ続けます。
もんくを言ったカニには、かたくて青い柿の実をなげつけて。
カニはつぶれて死んでしまいます。
ここから、かにの子どもたちの、あだうちがはじまります。
有名な昔話ですが、この絵本には「きび団子」が登場します。
昔話も「諸説あり」。
おもしろいですね。
かにむかし「読み聞かせボランティアにて」
この「かにむかし」絵本を、読み聞かせのボランティアで、読んできました。
場所
図書館にて
選書理由
テーマが「秋の味覚」だったため。
ご意見・感想
- 「きびだんご!? このお話はすこしかわっていておもしろかった。」
- 「うちの子が小さい時に読んでた本。なつかしい。」
- 「13分だとちょっと長いな。」
かにむかし「読み聞かせのコツ」
音読時間
13分
対象年齢
低学年
読み聞かせのポイント
この絵本は、二色刷りでホッとできる色合いの本です。絵もユニークでサルもにくめません。
遠目もききます。
文面は、方言があるので読みにくいような、読んでいてここちが良いような言い回しが続きます。独特なので、練習したほうがよさそうです。
ストーリーも繰り返しがきいています。
仇討ちのシーンは意外と短いので、ここからはゆっくり、少し時間をかけながら見せてあげて下さいね。
さるがいろりでせなかをあぶっているシーンから、怒涛の5ページです。
子どもたちには、このような昔話を語り継いでいきたいものです。「さるかに合戦」のお話の中でも、いろいろなストーリーがあることを知ったらおもしろがってくれますよ。
大作なので、読み聞かせの時間には気をつけてくださいね。
今回は「大型絵本」にしましたので、本が重く、しかも13分の長丁場。最後は左手がプルプルとしてきて筋肉痛になりそうでした。
昔話
長く読みつがれているものをまずは選ぶとよいです。
そういう本は、絵が古くさかったり、表現がおそろしかったりしますが、幼児期に読むと、根底のところで人生の教訓を得られるのではないでしょうか。
怒ってくれる大人が少なくなっている今、先人の知恵に頼ってみるのもいいかもしれません。
おまけ
実は、この「さるかに」こそ、私が昔読んでいたさるかにのお話なんです。
小学校低学年の学芸会で、なんと「うんこ役」に立候補した優等生だった私。
でも練習を続けていくうちに「うんこ」が嫌になってしまって、結局、先生から役をおろされたというほろ苦い思い出のある絵本です。
代役のあの子は、みごと笑いを取っていたっけ。
かにむかし「まとめ」
絵本「かにむかし」のご紹介でした。
読み聞かせボランティアの参考にしてください。
絵本「かにむかし」
音読時間:13分
対象年齢:低学年
小学校などでの読み聞かせでこころがけたいこと
にほんブログ村
読み聞かせランキング